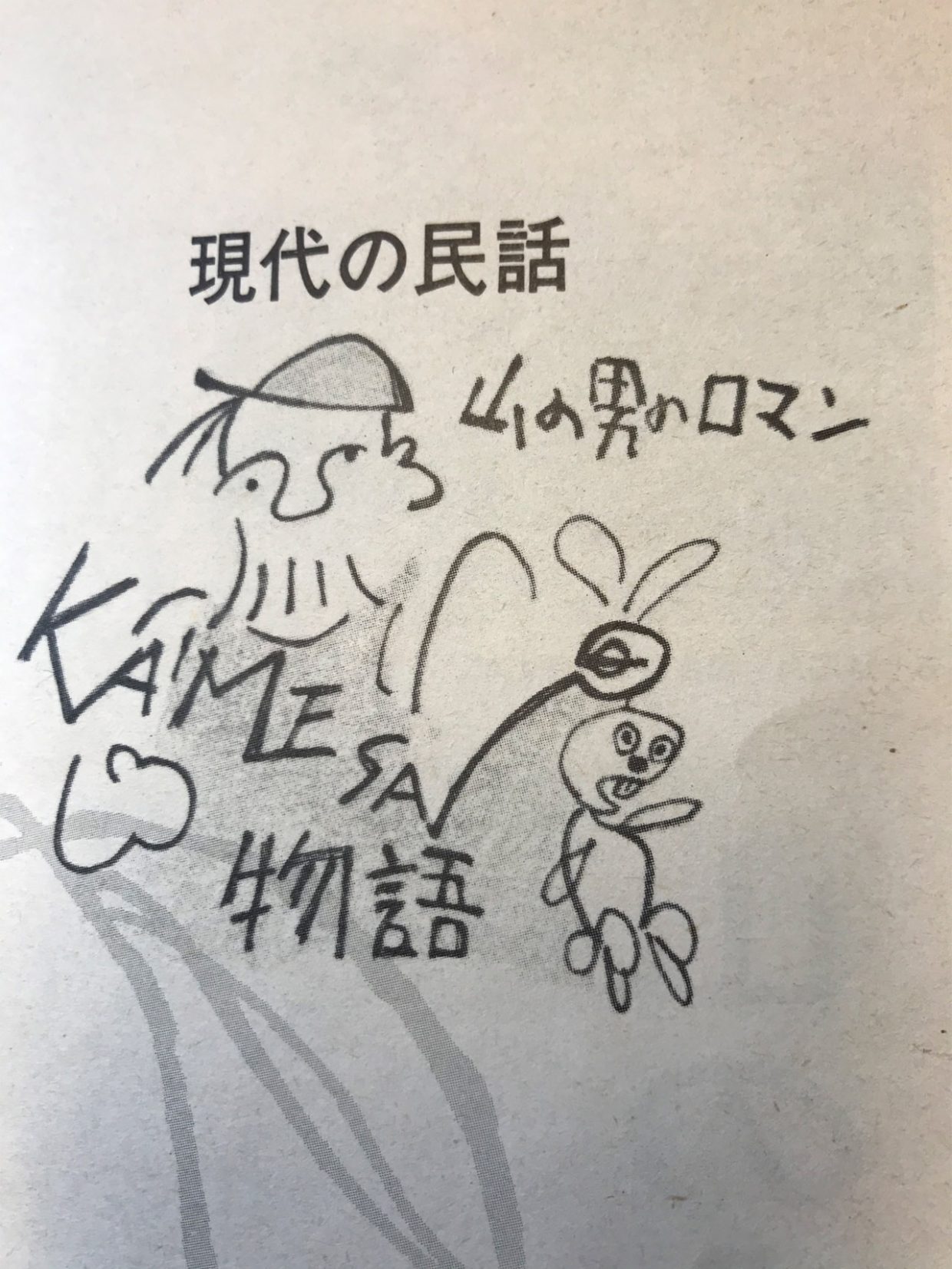昔笹ヶ峰に仙人がいた。仙人の名前を亀サといった。
昔、といってもそう遠い昔ではない。亀サは明治十ハ年の生まれである。
笹ヶ峰(標高1545メートル) その昔湖だった。笹ヶ峰湖といった。いまの野尻湖ほどの大きさだったという。妙高山はまだ活火山だった。何度となく大噴火をくり返していた。その後に地形は大きく変わり、地殻変動が起こった。ある年の大噴火で笹ヶ峰湖の水はすっかり乾上がってしまった。そして笹ヶ峰湖は化石湖となった。
笹ヶ峰は厳寒の地である。冬は二メートル以上も雪が積もる。ここの春は五月だ。深い残雪の間からふきのとうや水ばしょうが芽をほころばす。ブナや白樺がいっせいに緑をふき、春と初夏の高山植物の花が咲きだす。
笹ヶ峰には村があった。御新田といった。まわりの山から良材が出る。村人たちは木製品のほか、じゃがいも、あわ、ひえ、そばなどを作っていた。全盛期には三十戸近くの家があった。何度か冷害や作物の疫病に悩まされながらなんとか頑張ってきたが、明治三十二年じゃがいもの疫病が大発生してしまった。村人たちにとって御新田は地肉をわけた土地である。村人は話合った。考えぬいた。
何度集まって話し合っただろう。村人は決意せざるを得なかった。一人一人心の中に山は濃い影を落としていた。必死の思いで彼らはそれをはらいのけた。
御新田の人々は山を降りた。明治三十四年のことである。
亀サは明治十ハ年、その御新田に生れた。だから彼が村人とともに山を降りたのは十六才の時だった。生まれてから十六才まで笹ヶ峰で育った。だから村人の誰よりも亀サの中の山の影は大きかったといえる。亀サは山の心を心として育った。
山を下りた亀サはまるで違う世界へ足をふみこんだように思えた。からだに大きな空洞があいていた。毎日遠くにかすむ山を見つめていた。亀サは夢を見た。空洞の中に笹ヶ峰が広がっている。その高原から長い橋がかかっていて、橋は亀サのすぐ足元までのびていた。亀サは不安だった。一歩踏み出せば笹ヶ峰への橋を渡れる。森へとけこんでいくように思えた。恐る恐る足を出した。夢を見ているのか、現実なのか亀サにはわからなかった
亀サは橋を渡った。
亀サはくまだ
亀サは木の上でも岩の上でも平気でねむる。亀サは背は小さいが精悍である。亀サの目は茶色である。キラッとするどく輝いていた。
「俺は、亀だ」
亀サはぶっきら棒にいう。人々は亀サのことをいつか亀サと呼んでいた。
山を歩いていた亀サはある日穴ぐまの巣を見つけた。
茶色の瞳がキラッと輝いた。
「いるぞ」
何を思ったか亀サは穴へ手を突っ込んだ。驚いたのは穴ぐまである。いきなり人間の手が眼の前に現割れた。考えるひまもない。穴ぐまはその手にガブッと喰いついた。
「いてっ。はなせ」
亀サもあわてたが、穴ぐまの方も必死である。
「はなせっ」
いくら亀サだといってもはなすわけはない。
亀サは万身の力をこめて自分の手をひきもどそうとした。穴ぐまと力くらべである。亀サの力が勝っいた。次第に穴ぐまは引き出されてくる。ところが穴ぐまはずるずると引きづられながら、喰いついた手をはなそうとしない。穴ぐまはとうとう穴の入口まで引っぱり出された。穴ぐまの眼と亀サの眼があった。
「こんちくしょう」
亀サはいきなり穴ぐまの鼻に噛みついた。
すきをつかれて穴ぐまはびっくり仰天だ。やっと喰いついた亀サの手をはなした。
亀サの手には穴ぐまの歯あとが勲章のように残っていた。
亀サは本名を峰村助治といった。
1983、7 池宮 健一